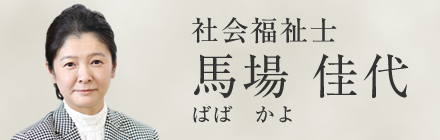平成31年4月26日、最高裁は子の引き渡しについて判断を下しました。最高裁に至る経緯は複雑です。要点のみをまとめると、別居した夫と同居している長男について、監護権のある母(裁判所の決定)が引き渡しを求めたところ、最高裁が「権利の濫用」だとして母の要求を認めなかったのです。
長男(9歳)は、母による監護を明確に拒絶していました。無理に連れて行こうとすると、呼吸困難に陥りそうになるほど、その意思は強かったようです。
最高裁の決定文を読むと、長男の監護権が母になっていることに疑問が湧きます。長男がこれほど母を拒絶しているのに、裁判所はどうして母を長男の監護者にしたのでしょうか。
あくまで推測ですが、監護者を決定する際に、長男の年齢が考慮されたと私は思います。長男は10歳に満たない年齢ですので、裁判所は長男の意思を重視しなかったのです。幼い子どもは明確な意思を持つ能力がないとされているからです。
ところが、実際には長男に明確な意思があった。つまり、監護者を決定する際の裁判所の判断が間違っていた。この間違いを正すために、最高裁は「権利の濫用」という最後の手段を使ったのです。
親権者(監護者)の判断要素として、(特に子どもが幼い場合に)「母親優先の原則」があります。「母親の役割を果たす人」の意味であって、必ずしも女性の親を優先する趣旨ではないと説明されることもあります。しかし、実務では(全てではないものの)「女性の親優先の原則」になっています。本件でも「女性の親優先の原則」が適用されたのでしょう。
以上の決定の報道に触れた時、私はある離婚事件が思い出されてなりませんでした。父母は別居しており、幼い子どもの監護権が争点となっていた事件です。
子どもは父と同居していました。母は調停室で子どもの名を呼び、泣いていました。調査官は子どもの監護者は母が望ましいと書かれた意見書を作成しました。裁判官は調査官の意見に従って、母を監護者とし父に対して子どもの(母への)引き渡しを命じました。
ところが、母は子どもの引き取りを拒否しました。実は、その直前に子どもに障害のあることが判明していました。母は子どもに障害があると知った途端に態度を豹変させ、子どもを見放したのです。
「母よ!逃げるな」
私は心の中で何度も叫んでいました。
私は「母親優先の原則」を批判したいのではありません。家族の紛争、特に子どもが関係する紛争は妥当な解決策を見出すのが難しいのです。しかも、当事者は感情的になりがちです。理屈では割り切れない問題ですから感情的になるのは当然です。それだけに弁護士や裁判所(特に調査官)の役割は重大です。私は弁護士の一人として、家族の問題を適切に解決することの難しさを改めて痛感すると同時に、慎重に事件に取り組まなければならないと考えています。
(丹波市 弁護士 馬場民生)